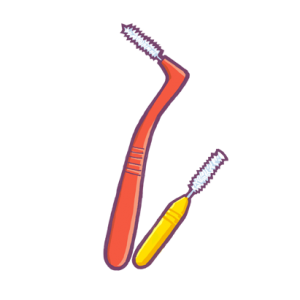今日もいいお天気ですね!
さて、皆さんは歯石に種類があるのはご存知ですか?
おおまかに分けて、歯茎の上につく黄白色の歯石と歯茎の中に隠れている部分につく黒い歯石の2つです。
みなさんが歯石がついてきた!と目に見てわかるのは歯茎の上についている縁上歯石といわれるものです。
通常の歯石取りの機械で1~2回で除去できるもので、定期的に歯石取りしてます!というのはこの縁上歯石のことなんですね。
対して、歯茎の下の隠れている部分についてくるのが歯肉縁下歯石と言われるもので、とても堅く、点状についています。
通常の歯石取りの機械では十分に除去できないので個別に一つずつ、個々の歯に合った器具をつかって丁寧に取っていきます。
取れた歯石をご覧になった患者様は
『えー!!こんなのがついているんですか・・・』とみなさんびっくりなさいます。
さて、この歯茎の中で育つ縁下歯石、歯を支えている組織に重大な悪影響を与えてしまうのです。
歯は歯茎ではなく、歯茎の下の歯槽骨といわれる骨に支えられています。
この支えの部分の骨が減ってしまうことが、歯周病、いわゆる歯槽膿漏です。
縁下歯石はこの歯槽骨の減る原因の一つなのです。
せっかくメンテナンスに定期的に通っていたとしても、縁下歯石がついている状態では歯茎の上の歯石取りを一生懸命やっているだけなので、残念ながら歯周病予防には効果がありません。
縁下歯石を除去したきれいな状態にしてから、メインテナンスに移行していくことをオススメいたします。
メインテナンスを継続的に行っている方でも、1~2年に一度程度は歯茎の中に歯石がついてきていないか、しっかり確認してもらうようにするともっと良い状態をキープできると思います。